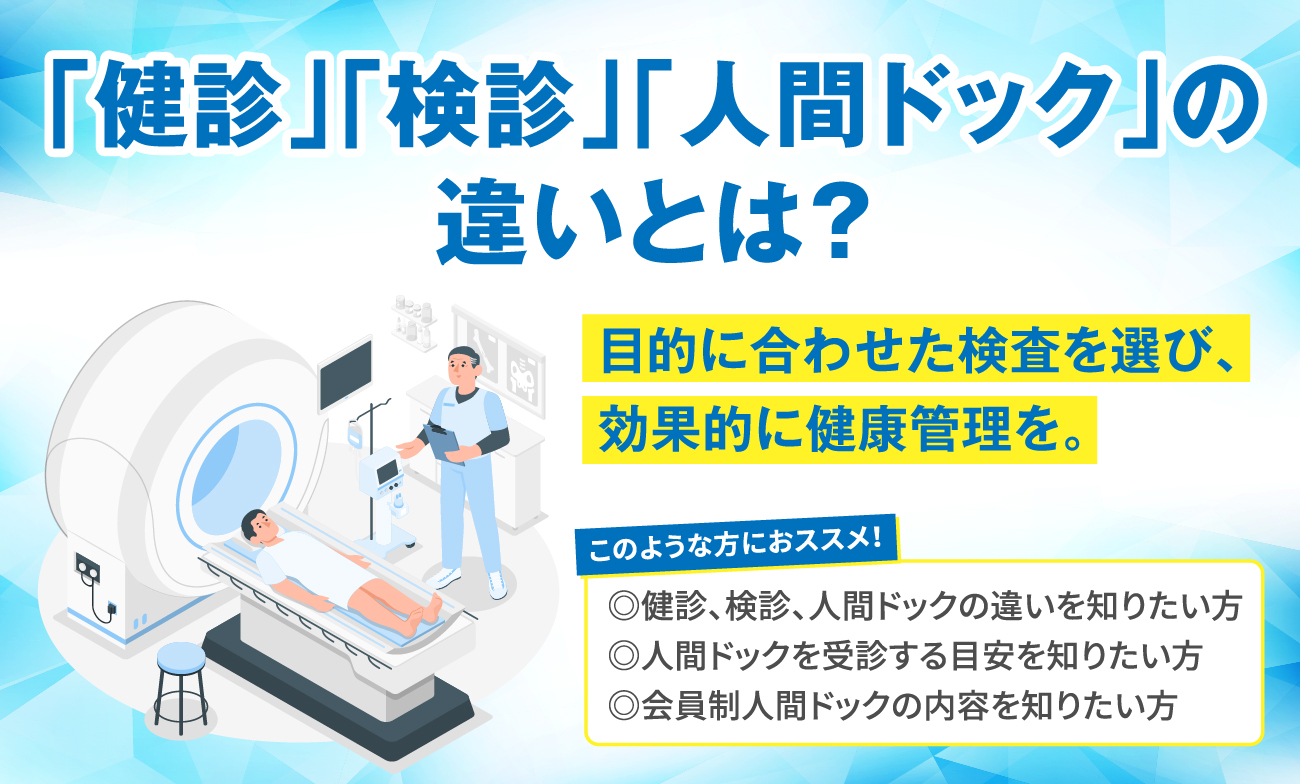
働く人の健康を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む「健康経営」のもと、健康への投資意識が高まっています。他方でがんの罹患率(りかんりつ)
は増え続け、健診や人間ドックの重要性が増しています。健診、検診、人間ドックなどの選択肢がありますが、自分に何が合っているか知りたいという方へ、それぞれの目的や検査内容の違いまで幅広く解説します。
◎健診、検診、人間ドックの違いを知りたい方!
◎人間ドックを受診する目安を知りたい方!
◎会員制人間ドックの内容を知りたい方!
・健康診断や人間ドックを受ける重要性
・人間ドックと健康診断の基本的な違い
・検査項目の違い
・人間ドックがおすすめの方は?
・会員制人間ドックを選ぶメリット
・まとめ
・会員制健康管理サービス「セコム健康くらぶKENKO」
「男性の2人に1人、女性の3人に1人が一生の中でがんに罹るリスクがある 」「3大疾病の死亡確率は65歳がピークになる 」、といった話を聞いても体力に自信のある時は問題として考えにくいものです。しかし、病気の多くは自覚症状なく進行するので、小さな病気のサインを拾い、詳細な検査や治療につなげる役割として健康診断や人間ドックがあります。
「健診」「検診」「人間ドック」がありますが、主な違いは目的と検査項目です。検査項目によって費用や検査に要する時間も異なります。この記事では企業の定期健康診断と人間ドック、検診と人間ドックなどの違いをわかりやすく解説します。
「健康診断」には、いわゆる企業健診と呼ばれる一般健康診断(定期健康診断)、自治体が40歳以上の方に向けて実施する「特定健康診査」などがあります。基本的にはそれぞれの目的に適した必要最低限の検査を行います。例えば、「一般健康診断」の目的は、業務が原因で労働者が病気になったり悪化したりすることを防ぐこと、「特定健康診査」は、生活習慣病の早期発見を目的とします。
健康診断の「健診(けんしん)」と同じ読み方で「検診」があります。これは特定の病気を調べるために行う検査のことです。「健診」での胃レントゲン検査で指摘され、「検診」でポリープやがんの有無を内視鏡で調べるようなときに使われます。健診、検診ともに健康保険や自治体で受ける以外は自由診療です。ただし、医師の判断により病気の疑いがある「検診」は、多くの場合保険診療で受けられます。
「人間ドック」は健康診断の一種です。一般健康診断よりさらに広く深い範囲を調べます。また「検診」の要素もあり、がんや心臓病などの検査もパッケージにした多様なプランがあります。PET/CT検査、MRI /MRAなどの精密な検査ができる機器を用いて、身体の状態を総合的に調べます。
一般健康診断の検査項目は、心臓病や脳梗塞などの原因となる生活習慣病の評価、肝硬変や慢性腎臓病につながる数値の評価など、一部の大きな病気の危険因子を調べる検査が中心です。病気の疑いや改善が必要な場合は、再検査や精密検査を受けます。
これに対して人間ドックは、一般健康診断で調べることが難しい病気の有無も一度に調べます。具体的には、食道、胃、大腸のがんを調べる上下部内視鏡検査、脳血管の状態を調べる頭部MRI
/MRA、骨粗鬆症の程度を調べる骨密度検査などが行われ、病気の有無やリスクを詳しく調べます。
健康診断にかかる時間は年齢や検査内容で異なりますが、40代の一般健康診断(企業検診)では一般的に長くて3時間程度です。人間ドックは検査項目により異なりますが半日から、1泊2日で行います。
| 種類 | 費用の目安 | 時間 |
|---|---|---|
| 一般健康診断 20代 | ・公費の場合は無料または安価 ・健康保険の場合は保険組合による (基本的な検査は無料が多い) |
約1時間 |
| 一般健康診断 40代 | ・公費の場合は無料または安価 ・健康保険の場合は保険組合による (基本的な検査は無料が多い) |
約3時間 |
| 人間ドック+単体検診 基本的な人間ドックと一部のがんなどの検査 |
自由診療 3万円〜8万円 |
半日から1日 |
| 人間ドック 全身のがん・脳疾患含む総合的な検査の場合 |
自由診療 10万円~40万円程度 |
1泊2日 |
※人間ドックは、国民健康保険、社会保険、民間の保険から補助金や助成金が受け取れる場合があります。
一般健康診断の検査項目です。以下の10項目からなります。労働安全衛生法に基づいた、国から義務付けられている法定健診の項目です。
40〜74歳の人が受けられる生活習慣病の早期発見を目的とした「特定健康診査」では、メタボリックシンドロームに注目し、腹囲の測定、空腹時血糖、服薬歴、喫煙歴などの項目が追加されます。
人間ドックで受けられる検査項目は、30〜100項目にもおよび、オプション検査を組み合わせる場合もあります。検査目的に合わせて半日、日帰り、1泊2日などのプランがあります。
以下は、3大疾病(脳卒中・心臓病・がん)と生活習慣病の早期発見を主な目的としたコースの検査項目です。PET/CT検査、頭部MRI、頭部MRAなどを駆使した精密検査が特徴。認知機能や筋力のチェックも取り入れた例です。
| 項目 | |
|---|---|
| 問診・診察 | |
| 身体測定[身長・体重・腹囲・血圧・握力検査] | |
| 眼の検査[視力・眼圧・眼底] | |
| 聴力検査 | |
| サルコペニア検査[握力・椅子立ち上がりテスト・筋肉量] | |
| 骨密度・筋肉量検査 | |
| 血液検査 | 一般検査 |
| 腫瘍マーカー(AFP (aフェトプロテイン)、CEA、CA19-9、PSA、CA125) | |
| ビタミンD | |
| 尿検査(尿定性・尿沈渣) | |
| PET/CT検査(上顎部~大腿部) | |
| 脳・脳血管の検査 | 頭部MRI、頭部MRA |
| 甲状腺の検査 | 甲状腺機能(TSH、FT4)、甲状腺超音波 |
| 動脈硬化の検査 | 脈波伝播速度、下肢/上肢血圧比、頸部超音波 |
| 循環器の検査 | 安静時心電図、心臓超音波、NT-proBNP |
| 呼吸器の検査 | 胸部CT、呼吸機能、喀痰細胞診 |
| 消化器の検査 | 上部消化管内視鏡、ペプシノーゲン、ピロリ菌、腹部超音波、便潜血 |
| 泌尿器の検査 | 膀胱超音波、PSA(腫瘍マーカー) |
| 乳腺の検査 | マンモグラフィ、乳腺超音波 |
| 婦人科の検査 | 内診、子宮頸部細胞診、経膣超音波、骨盤MRI |
また、時間が取れない人や特定の疾患を調べたい方に向けた、半日(3時間半程度)の人間ドックもあります。腫瘍マーカーを含む詳細な血液検査と、PET /CT検査を組み合わせた、全身のがんを重点的に調べるコースがその一例です。
健康診断は多くの人が毎年受けますが、人間ドックは任意の健康診断なので受診は自己判断です。かかりつけの医師がいる場合は相談し、下記のポイントも参考に検討しましょう。
例えば、がんという病気は早期発見と初期段階の治療で予後や生存率が大きく変わります。初期のがんを見つけるには健康診断では難しく、上下部内視鏡検査やPET/CT検査、MRI/MRA検査など精密な画像診断を組み合わせて調べる必要があります。健康診断で気になる項目がある場合のほか、病気のリスクを全体的に知りたい人に人間ドックはおすすめです。
40歳以上になると、がんや心臓病(心筋梗塞や狭心症)、脳血管疾患(脳卒中、脳梗塞等)の命に関わる病気のリスクが大きく高まります。生活習慣病はこれらの危険因子となるため、40代以上で高血圧や脂質異常症、糖尿病、肝機能の数値などを指摘された方は、年に一度の人間ドックが推奨されます。また、がんの家族歴のある方も気にかける必要があります。
医療機関では専門領域ごとに分業化が進んでいます。病気の種類、症状や疾患のある部位、性別や年齢により、循環器、呼吸器、消化器などに分かれ、それぞれの診療科で専門の医師が担当します。人間ドックの検査項目を診療科ごとに検査すると膨大な時間がかかり現実的ではありません。人間ドックは複数の検査を1〜2日で完了でき、一度の機会で精密に検査するのでとても効率的です。
人間ドックは幅広い病気の早期発見と治療の入り口として機能します。ただし「検査して終わり」では意味がなくなります。大切なのはその人自身が結果を理解し、自分事として捉えて生活習慣の改善に向けて行動したり、適切な治療につなげることでしょう。
長期の健康管理を目的とする「会員制人間ドック」とは、慢性的な病気がある方だけでなく、定期的な健康チェックやアドバイスを受けたい方に向けたサービスです。ここからはセコムの会員制健康管理サービス「セコム健康くらぶKENKO」(以下、KENKO)の特徴について紹介します。
会員制人間ドックとは、人間ドックと継続的な健康管理を組み合わせた総合的なサービスの総称です。例えば、KENKOでは以下のような特徴があります。
主治医による人間ドックの検査結果説明、体調不良時の診察、ちょっとした日々の健康相談まで総合的に会員を見守る体制があります。診察は完全予約制です。
KENKOでは、健康管理やフォローアップを人間ドックと同等のサービスの柱として位置付けています。検査は病気の早期発見に欠かせないものですが、その後の対策がなければ改善につながりません。忙しさや知識不足から結果を放置することにならないよう、二次検査から治療への移行、食事・運動といったライフスタイルの改善に至るまで全体的にフォローすることが会員制人間ドックの役割です。
人間ドックの検査結果は専門的で理解が難しいことがあります。そのため、数値の変化が病気とどう関係しているか、将来的にどのようなリスクがあるかを理解するには専門知識が必要です。
KENKOでは、会員様が納得してご自身の身体と向き合えるよう、主治医が時間をかけて結果を説明します。説明の後は、会員様に合わせて経過観察、定期検査、提携医療機関への紹介などを行います。
主治医とは、患者のこれまでの病気や健康上のリスクを把握し、日々の診療や治療に継続的に関わる医師のことです。わかりやすく言えば、「その人の健康状態をもっともよく理解して、最適な対応をしてくれる医師」のことをいいます。そのため、「主治医制」による会員様のフォローアップ体制はKENKOの大きな特徴の1つです。
「主治医制」のメリットは、会員様の検査結果から日々の診療内容まで、情報がひとりの医師のもと一元管理されることです。
例えば、体調不良で原因がわからず「どの医療機関のどの診療科に行けば良いか」迷うことがありますが、KENKOでは主治医が検査結果に加え、直近の診療内容、既往歴まで考慮して治療につなげます。必要に応じて専門の医師と連携し、その内容はまた主治医に共有されます。ひとりの医師が検査から治療まで見守る「心の安心」にも配慮した診療体制です。
KENKOでは医師だけでなく看護師、管理栄養士、保健師、事務スタッフのチームが目配り気配りを心がけ、きめ細やかにサポートします。健診結果に異常の有無に限らず、会員様の食事や運動習慣、健康状態をチームで共有してアドバイスします。診察・相談は完全予約制で待ち時間のストレスがなく相談しやすいこともメリットです。
会員サービスには、併設の医療機関「医療法人社団あんしん会 四谷メディカルキューブ」での主治医や各専門の医師による外来診療(完全予約制)も含まれます。治療や検査が必要なときには保険または自由診療での受診が可能です。かぜ症状から季節性のアレルギー症状などの困りごとも気兼ねなく相談することができます。日頃の診療を通して主治医に集まる情報の蓄積が、いざという時の備えになります。
人間ドックの機会が心身にとって特別な時間となるよう、食事も充実しています。フランス料理の巨匠三國清三シェフが手がける院内レストラン「ミクニマンスール」では「美しく、おいしい、心と体に優しい料理」 をコンセプトにカロリーと栄養バランスに配慮したメニューを提供しています。人間ドック受診の際には昼食が用意されます。
今回は、健康診断と人間ドックの違いから会員制人間ドックまで、目的や検査内容を解説しました。健康診断は年一回受ける機会があり、誰でも受診しやすい仕組みがありますが、年齢や健診結果によっては自主的に単体検診や人間ドックを取り入れることが大切です。
特にがんや脳血管疾患など幅広い病気のリスクを知りたい方は、人間ドックを検討してもよいでしょう。また、健康管理を徹底して病気のリスクをできるだけ遠ざけたい方には会員制人間ドックという選択肢もあります。検査の種類を知り、健康管理に役立てることが大切です。
あんしんのセコムが提供する会員制健康管理サービス「セコム健康くらぶKENKO」では、高精度の医療機器を駆使した総合人間ドックを提供しています。脳腫瘍や脳梗塞の早期発見につながる頭部MRIや、がんの発見に威力を発揮するPET/CT検査、小さな肺がんも見逃さないマルチスライスCTなど、さまざまな検査を受けられます。
会員ひとりにつき、一人の主治医と保健師、看護師、栄養士からなるチームが、健康的な日常生活や食事、運動習慣、体調管理まで丁寧にサポートし、アドバイスを行います。また、会員専用安心ホットラインでは、病気や身体に関するご相談に24時間体制で対応しており、お気軽にご相談いただけます。